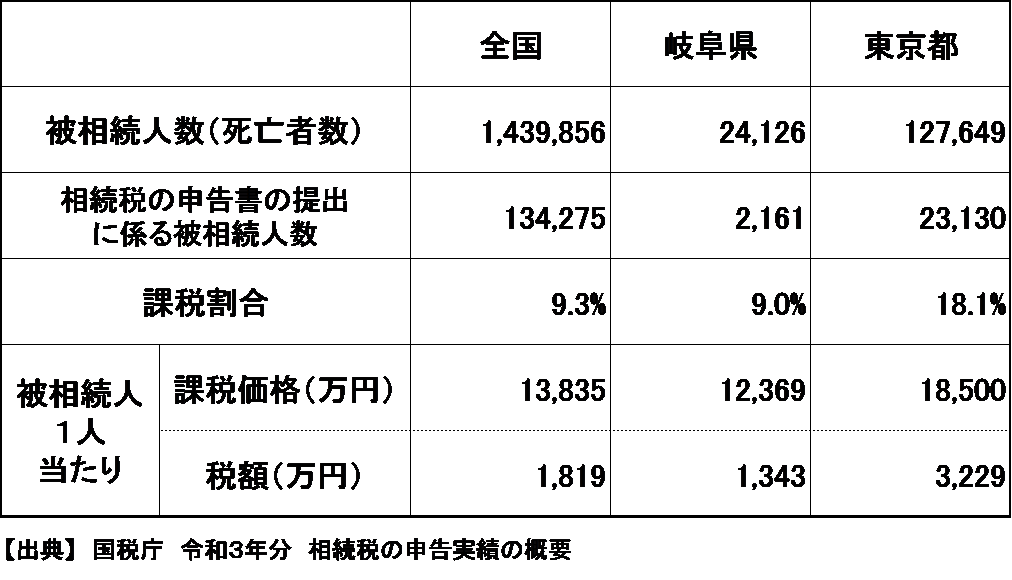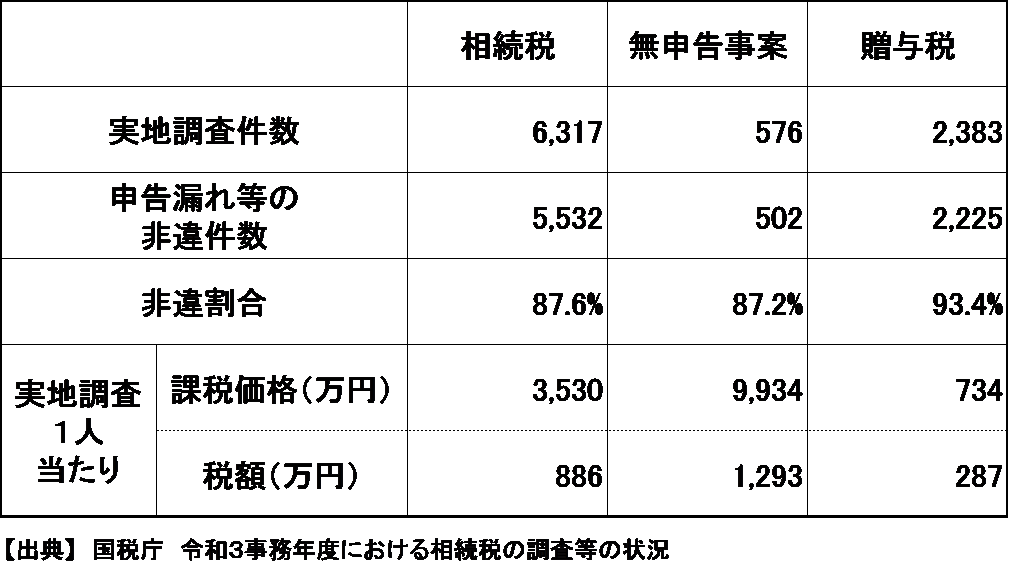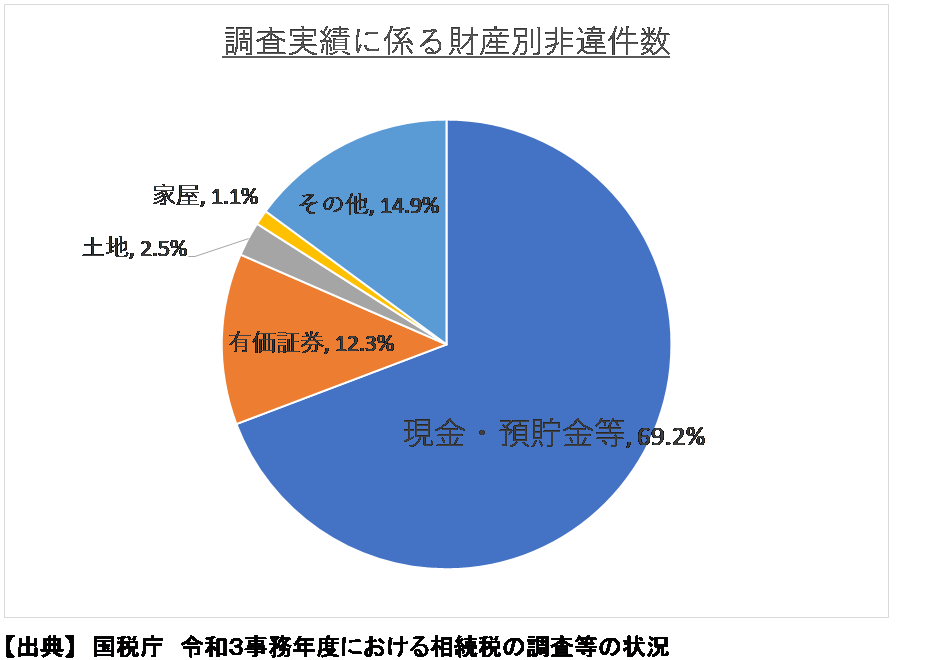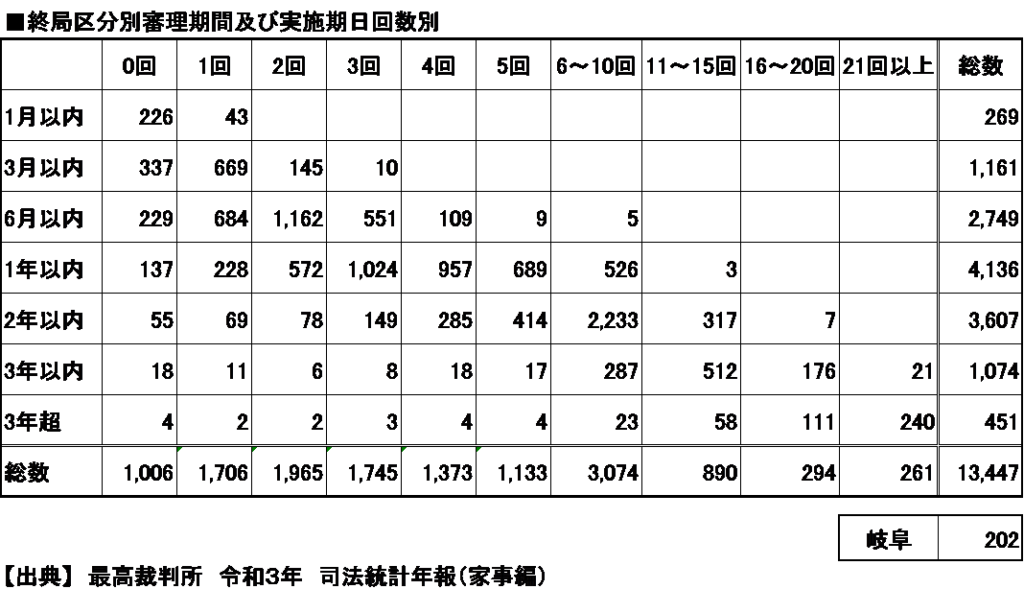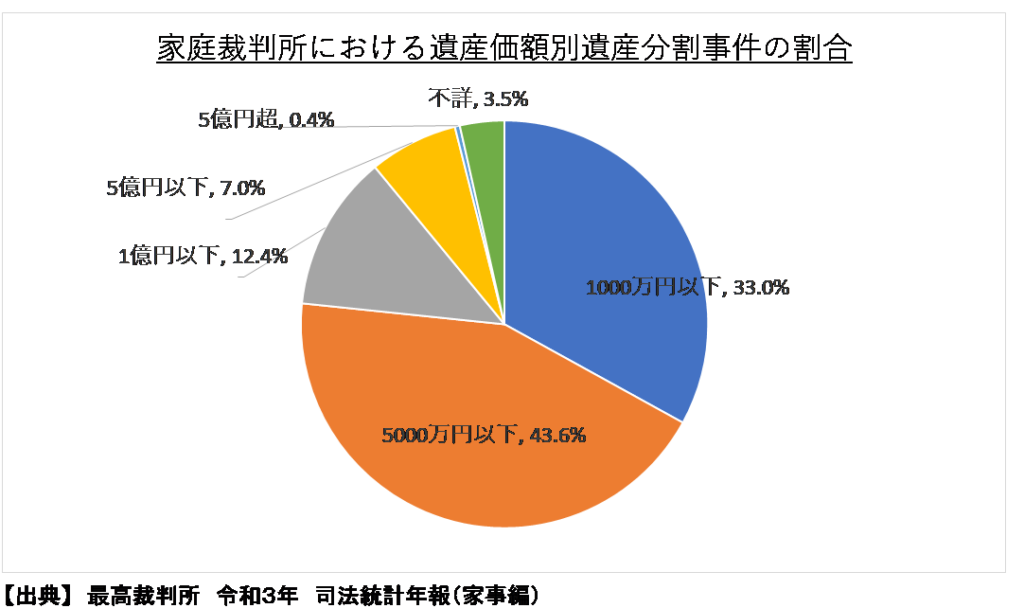卓話者 国際ロータリー第2630地区 直前ガバナー 浦田幸一様
浦田幸一様
ロータリアンの指針最も奉仕する者最も多く報いられる 超我の奉仕
シェルドン (※1)のスピーチ (ステークホルダー資本主義の原形)
1910 年 米国ロータリークラブ第一回年次大会 シェルドンのスピーチ シェルドンは、かねてから彼が考えていた奉仕哲学に関するスピーチを行いました。事業上得た利益は、決して自分一人で得た利益ではありません。従業員、取引先、下請け業者、顧客、同業者など、自分の事業と関係を持つすべての人々のおかげで得たことに感謝し、その利益を適正にシェアする心を持って事業を営めば、必ず最高の利益が得られることを自分の職場で実証し、その方法こそが正しいやり方であることを、地域全体の職業人に伝えていかなければなりません。 」
まず、ロータリアンの企業が職業奉仕理念に基づいた正しい事業経営をし、それによって事業が継続的発展をすることを実証すれば、必ずや他の同業者たちもその経営方法を見習うはずです。それが結果として、業界全体の職業倫理高揚につながるはずです。これが“最も奉仕する者、最も多く報いられる” (He profits most who serves his fellows best )の真意です。」
ステークホルダー資本主義
2020年1月のダボス会議(世界経済フォーラム)の主題となりました。これは、企業は株主の利益を第一とするべしという「株主資本主義(新自由主義)」とは違い、企業が従業員や、取引先、顧客、地域社会といったあらゆるステークホルダーの利益に配慮すべきという考え方であります。100年も前にシェルドンはこのことを述べており、いかに彼が思慮深く聡明だったかが偲ばれます。
ロータリーの真髄は職業奉仕 対 社会奉仕こそが ロータリー運動の真髄 1920年前後の論争
これに対して、[奉仕活動の実践]に重きをおく実践派は、現実に身体障害者や貧困などの深刻な社会問題が山積し、これまでにロータリークラブが実施した社会奉仕活動が実効をあげていることを根拠に、シェルドン派とことごとく対立。実践派から見れば、奉仕の機会を見出して、それを実践することこそロータリー運動の真髄であり、単に奉仕の心を説き奉仕の提唱に止まるシェルドン派の態度は、責任回避としか写らなかったのです。両派の論争は、個人奉仕と団体奉仕、さらに金銭的奉仕の是非にまで発展して、綱領から社会奉仕の項目を外せという極論まで飛び出すほどでありました。
目の前で苦しむ人達を見過ごせない!
このような大論争の起こった素因は何かというと、それは、当時、米国各地のロータリークラブが精力的に取り組んでいた「身体障害児」救済の問題。ロータリークラブが身体障害児問題に関心を示し、最初にこれに取り組んだのは、1913年頃、ニューヨーク州シラキューズR.C. であったといわれており、次いでオハイオ州のトレドR.C.が行動を起こしました。そのきっかけとなったのは、会員の一人が街で見かけた古ぼけた自家製の車椅子に乗った少年から話を聞いて、身体の不自由な子どもたちが世間から見捨てられ、教育の施設もなく悲惨な環境にあることを知って、クラブ例会において、力強い訴えが全会員の琴線に深く触れ、活動につながりました。この問題を語るときに、最も忘れ難い人物に、エリリアR.C.のエドガー・アレンがいます。
決議23-34と四大奉仕 シェルドンが提唱する、企業倫理、自己責任や事業主の責任、そしてこれらを行うとともに、利益の再配分や円満な労使関係の改善をはかったことに対して、経営学者としては高い評価を受けますが、シェルドンの考え方に対して、当時の国際ロータリーの指導者層の中の保守的な人たちからは批判が強く、シェルドンの理念がロータリーの奉仕理念として尊重されていることに反発を持っていた元会長のグループや、身体障害者対策などの対社会奉仕活動に目覚めた実践派のグループなどが勢いを伸ばしてゆき、彼らはロータリー運動の中心に、社会奉仕活動を据えました。シェルドンの奉仕理念には社会奉仕の概念は全く存在せず、もし他の分野の奉仕活動が必要ならば、正しい経営学の遂行によって得た利潤から個々のロータリアンが行えばよいという考えでありました。 大論争の両者を立てる形で・・・。
1923 年に制定された決議23-34 は、この二つのモットーを同列に並べ、条件を付けながらも団体的奉仕活動を認めた。1927 年のオステンド大会おいて、唯一であったロータリーの奉仕理念「He profits most who serves best」を四分割して、もっとも重要な「 職業奉仕 」を奉仕の一分野にし、「社会奉仕」「国際奉仕」「クラブ奉仕」としました。これがロータリーの四大奉仕であります。
決議23-34 制定の経緯 1922 年Rotary International(国際ロータリー、以下RI)理事会はエリリア、トレド、クリーブランド各クラブよりの共同提案を受けて、決議22-17を採択して、身体障害児に対する対策を奨励します。しかし、この決議を行った直後に開催された理事会では、身体障害児救済の事業に狂奔することを戒める理事会決定を行っています。 理事会の態度は更に二転三転し、1923 年のセントルイス大会において「決議23-8 障害児、並びにその救助活動に従事する国際的組織を支援せんとする障害児救済に関する方針採択の件」という、これは積極的に身体障害児対策を推奨し国際身体障害児協会の仕事をロータリーが代行し、その費用を援助するためのものであり、理論派は大反対でした。シカゴ・クラブの会長ポール・ウェストバーグたちは、RI が奉仕活動の実践をクラブに強要することを禁止する決議23-29を提案するという反対キャンペーンにでます。セントルイス大会の大混乱を避けるために、双方の決議提案を撤回する代わりに決議 23-34 を提案するということによって、この論争に終止符が打たれることになり、決議委員長の指名を受けたウイル・メーニァは 4 名の委員と共に決議23-34を書き上げ、この 1,000 語からなる決議は直ちに大会で皆に披露され、一言の訂正もなく採択されました。
日本のロータリーの原点
「 職業奉仕 」「社会奉仕」「国際奉仕」「クラブ奉仕」とした。四大奉仕であります。
RI における職業奉仕消滅化 ロータリーの職業奉仕に対する考え方も大きく変わってきました。 1987年に RI の職業奉仕委員会は、「職業奉仕に関する声明」を発表しますが、「クラブが職業奉仕を実践する」という文章について問題が生まれてきます。シェルドンの職業奉仕理論の中からは、クラブが職業奉仕の実践を行うという考え方はないからであります。 職業を持っている個人だから職業奉仕の実践ができるのであって、職業を持たないロータリークラブがどうやって職業奉仕の実践をするのかということであります。さらに RI はその具体例としても職場訪問、優良従業員の表彰、ボランティア活動をあげていますが、 これらは職業奉仕活動とはいえません。
ロータリーのような国際的な組織では Grovel Standardに基づいて組織管理をする必要があるのですが、現在の RI はアメリカを中心にした American Standard を押し付けているようで、ジョン・ヒューコ・スタンダードかもしれません。 ロータリーが他の奉仕団体と異なる唯一の特徴が、職業奉仕の理念と実践であったのに、現在の RI は 職業奉仕に関する関心がほとんどありません。
人道的なものに限られたボランティア組織化の一途をたどっており、ロータ リーを世界最大の NPO と位置づけているようで、ボランティア活動を優先するあまり、例会が軽視され、ロータリーの魅力をそぐ大きな原因となっています。毎週 1 回の例会は会員相互が職業上の発想の交換を通じて親睦を深めると同時に奉仕の哲学を研鑽する生涯学習の場でもあります。米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道場」と述べています。「入りて学び出でて奉仕せよ 」という言葉を忘れてはならないと考えます。
職業奉仕から学ぶ 最も奉仕する者最も多く報いられる 超我の奉仕 を持って臨む
家族を愛し 仕事仲間・従業員を慈しみ 人のお役に立つ
(文中敬称略)
直前ガバナー 浦田様と田邊会長
故金会員、森会員、浦田様、田邊会長